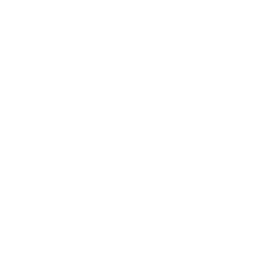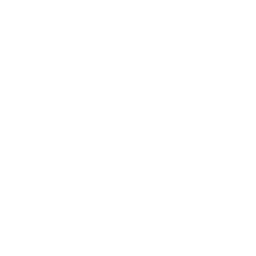知育がもたらすさまざまな効果とは?知育方法についても解説
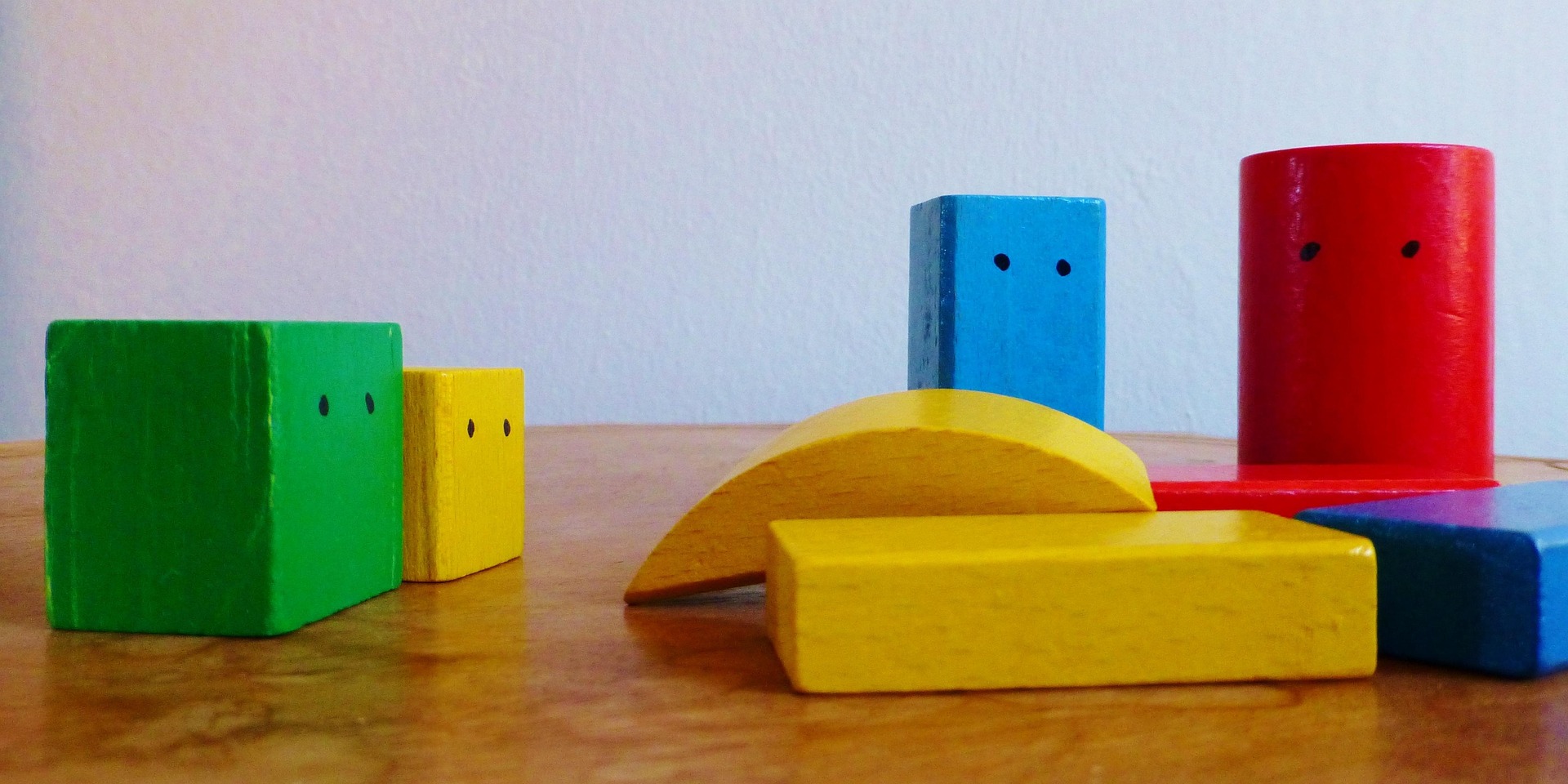
幼児教育を行う上で、推奨されることの多い知育ですが、具体的な意味を理解している人は少ないのではないでしょうか。今回は、遊びとの違いを踏まえた上で、知育がもたらす効果や、具体的な方法などを解説します。
この記事を読むための時間:3分
知育とは?
知育とは、遊びを用いて子どもの知力や知能を育てる教育を指します。幼少期から行うことで、非認知能力を高めたり、コミュニケーション能力を高めたりできます。
三育の1つ
知育は、三育の1つです。知育の他には、人としての道徳心を育てることを目的とした「徳育」、運動能力を高めることを目的とした「体育」があります。三育では、知育・徳育・体育の3つをバランスよく育てることが重視されています。
遊びとの違い
知育は、知力や知能を伸ばすことを目的として行われるのに対し、遊びは子どもが自由に楽しむ活動です。ただし、子どもが行う遊びの中にも、知育が含まれるケースもあります。しかし、知育は子どもの興味関心や年齢に合わせて、明確な目標を守って行われるという点で違いがあります。
知育がもたらす効果
知育がもたらす効果には以下があげられます。
- 子どもの知能アップが期待できる
- 自発性を育てられる
- 巧緻性を高められる
子どもの知能アップが期待できる
知育を行うことで、子どもの知能アップが期待できます。特に、幼児の脳はとても柔軟で、吸収性が高いことが知られています。脳が急成長する時期に知育を行うことで、子どもの知能アップが期待できるでしょう。
豊かな人格形成につながる
知育は、知能だけでなく自発性やコミュニケーション能力を育むことにもつながります。論理的思考力を育むことで、相手の感情を理解する共感性も高められるでしょう。
巧緻性を高められる
巧緻性は、手先をうまく使って細かい作業を行う力を指します。知育には、手先を利用するものが多く、巧緻性を高めることにつながります。近年では、小学校の入学試験などでも巧緻性を試す問題が出題されるなど、その重要性に注目が集まっています。
知育の方法
以下は、具体的な知育方法の一例です。
- 教材や玩具を利用する
- アプリを利用する
- 知育教室に通わせる
- 日常生活の中に知育を取り入れる
教材や玩具を利用する
知育教材や知育玩具などを取り入れることで、誰もが家庭内で知育に取り組めます。知育教材は、絵本やワークなどさまざまな形態のものが出版されています。年齢や能力に合わせて無理なく取り組めるものを選んでみましょう。
また、知育玩具には、パズルや積み木、木製玩具などがあります。遊び感覚で取り組めるのが魅力です。
アプリを利用する
近年、スマートフォンやタブレットの普及と共に、知育アプリも登場しています。外出先や車の中など、場所を選ばずに短時間で取り組めるのが魅力です。ただし、スマートフォンやタブレットの長時間利用を防ぐために、利用時間を区切って、適切に使用するのがポイントです。
知育教室に通わせる
より専門的に知育に取り組みたい方は、知育教室に通わせるのも1つの手です。子どもの年齢に応じて色々なコースが用意されているため、まずは体験レッスンに参加してみましょう。
日常生活の中に知育を取り入れる
日常生活も、ちょっとした工夫で知育となります。たとえば、料理も、段取りを組むことや、手先を動かすことにフォーカスすれば知育につながります。
また、庭の手入れも、植物や昆虫の名前を調べながら行うことで知育につながります。少しの工夫で日常生活の何気ない行動が知育につながるため、色々なアイデアを考えてみましょう。
知育を積極的に取り入れよう
今回は知育について、効果ややり方などを詳しくご紹介しました。幼児期から知育を行うことで、子どものさまざまな能力を高めやすくなります。教材や玩具、アプリなどを利用して、気軽に知育を取り入れてみましょう。